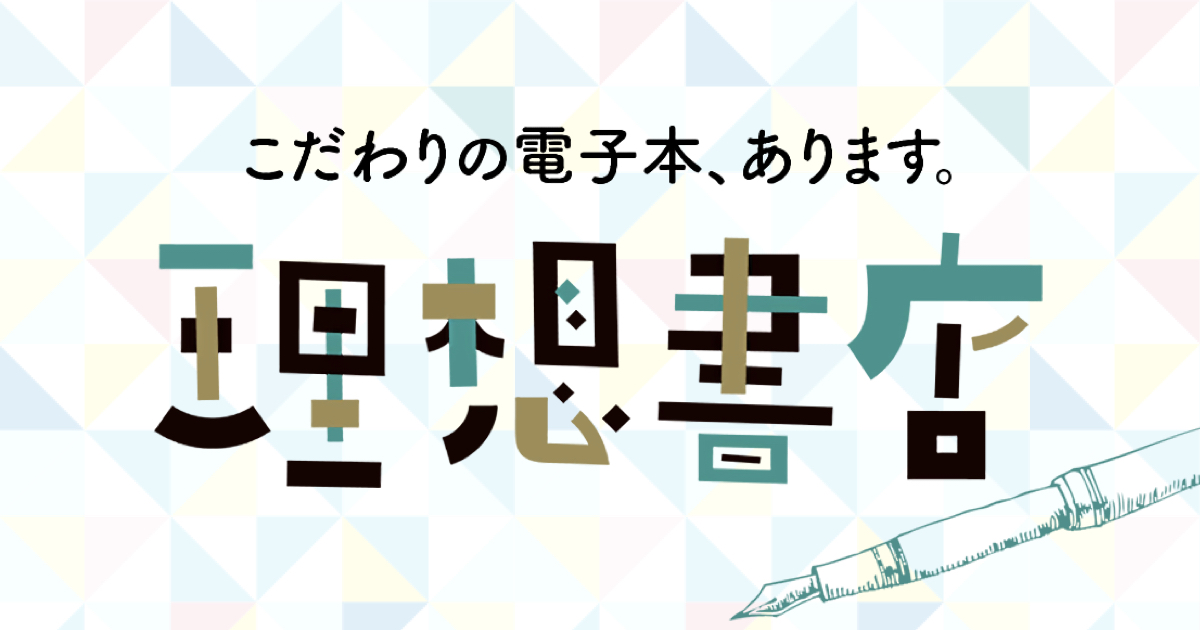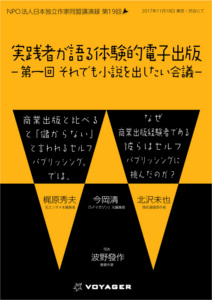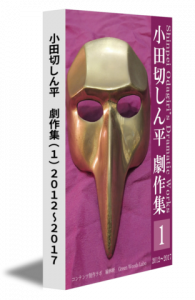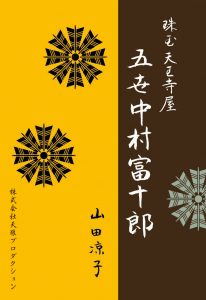片岡義男『窓の外を見てください』(講談社)刊行記念として開催されたトークイベントの全貌を収めた映像を公開いたしました。
以下リンクから、書き起こし記事と共にご覧ください。
名手が明かす“最高の小説のつくりかた” 第2弾(片岡義男.com)
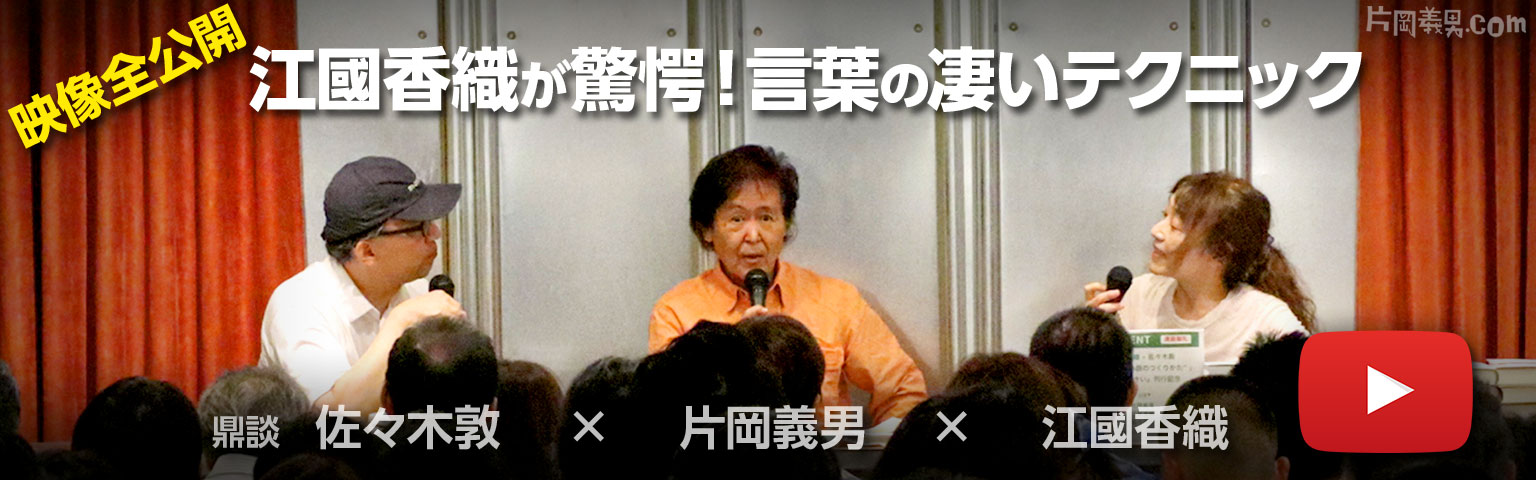
自身も片岡ファンであるという作家・江國香織さんと、片岡さんと数々の対談をされてきた批評家・佐々木敦さんを交え、当日集まったお客様は100名以上。片岡さん自ら語る小説の書き上げ方、江國さんが分析する作家としての言葉のあやつり方など、小説が生まれる現場の話が満載です。
ボイジャーの推進する「作家・片岡義男 全著作電子化計画」で公開される本はすべてRomancerでつくられて届けられています。
いろいろ情報
Romancer5周年

2014年7月1日にRomancerがスタートして、5年が経ちました。この間のみなさまのご支援に心から御礼申し上げます。ありがとうございました。
ご利用の現状をお知らせいたします。
- 登録ご利用者数 7,700人
- 公開作品数(無料での一般公開)1,900作品
- 制作された作品数 57,000作品
実際にRomancerを利用してAmazon Kindle、楽天KOBO、BookLive!、紀伊国屋書店という代表的な書店での販売をされている事例は多数あります。『栗本薫・電子本シリーズ』も「片岡義男.com」の『短篇小説の航路シリーズ』も、すべてRomancerでつくられて届けられているものです。そして、一番みなさまに読んでいただいた本は『荒れ野の40年 ワイツゼッカー連邦大統領演説全文』で、7月1日0時時点での閲覧実績は7,791回となっております。デジタル出版で7,000、8,000、更には10,000を越える読者を獲得することが夢ではないことがお分かりいただけることでしょう。
デジタルに覆われた世界の中で…
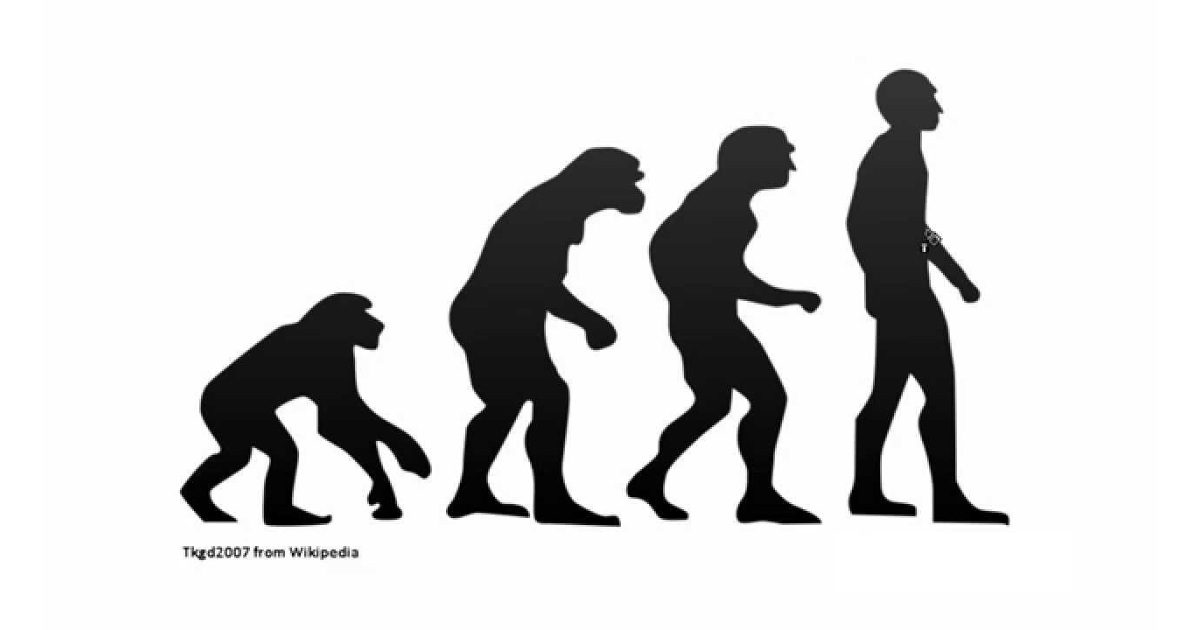
デジタル……そこにあるのが当たり前で、何の疑問もなく毎日使っています。いつどこで生まれたのか、誰がどうやって作ったのかさえよく知らないままに、インターネットの恩恵を受けている。しかしワンクリックで何でも届けてくれる便利な仕組みの起源には、暗い側面もあります。たとえば、現在のコンピュータの基礎を築いた功労者とされる数学者ノイマンは、原子爆弾開発のためのマンハッタン計画に参加し、京都と広島への原爆投下を軍に進言しています。
ポツリ一言 これは地獄だ

作家・片岡義男が写真と一文で綴るシリーズ「東京を撮る」は、すでに一部で公開が始まっています。 下高井戸、経堂、下北沢、谷中、町田と、東京の街中を歩き自らシャッターを切ってお届けしようというものです。でもしかし、送り手である片岡チームの私たちでさえ、一体何がしたいのかよく分かっていませんでした。ですからいわば「そのまんま」だすしかなかったのです。
*ここまで聞いてご興味あれば今すぐにでもご覧になれます
→片岡義男・書き下ろし作品
https://kataokayoshio.com/original#tokyo

アメリカを知っているのか?

広島を訪問したこともあるオバマ大統領は、2009年にプラハで核兵器のない世界の実現を目指すと発言しました。しかし、その後のアメリカはどうなったでしょう。
日本では8月15日は「戦没者を追悼し平和を祈念する日」と定められています。アメリカにも戦没者を追悼する日があります。戦没将兵追悼記念日、英語でMemorial Dayと呼ばれる日です。戦争でアメリカ人も大勢死んでいます。敵も味方も多くの血を流し、家族を失うのが戦争です。けれどなお、戦争は繰り返されています。
青い海の写真で避暑を…

写真家・佐藤秀明と作家・片岡義男による、写真と対話の本『海まで100マイル』。紙の本は絶版となって久しい。37年の時を経て、この本がデジタルで甦ります。ただの復刻ではありません。佐藤秀明の手によって写真が大幅に入れ替えられたのです。コメントも新たに挿入されて生まれ変わりました。
猛暑の日にジープが来た
連日の猛暑。このような暑さのなか太平洋戦争のサイパンや沖縄で、米軍のジープは、土埃にまみれて走っていたのです。そしてその後、朝鮮半島へ送られたのもこのジープでした。
インターネットでジープを検索すれば、ファミリー、レジャーといった言葉が目に入ります。平成生まれの若者たちにとってのジープは、山登りでしょうか。軍事マニアなら、米軍を連想する人もいるかも知れません。けれど、実際に終戦直後の焼け野原の東京で迫ってくるジープがどんなイメージなのかを知っている人は少ないです。
ビートルズがやって来た日

52年前の今日、1966年6月29日未明にザ・
当時の日本の混乱ぶりは相当なもので、
そんな中で3日間に行われた5公演は前座を含めて1時間、
デジタル出版の困難、そして喜び

「小説を出したいかー!」
そんなかけ声とともに始まった、2017年11月のトークイベント「それでも小説を出したい会議」。商業出版の経験者でありながら、「儲からない」と言われているセルフパブリッシングに挑戦した3人の登壇者が大いに語りました。彼らはなぜデジタルを選んだのか? 電子本を出すメリットとは何なのか? その答えが、この冊子に詰まっています。
印刷版:972円(税込)
電子版:777円(税込)
登壇者
今岡清(『S-Fマガジン』元編集長)
梶原秀夫(元エンタメ本編集者)
北沢未也(現役漫画原作者)
司会
波野發作(兼業作家)
誰でも突然モシュになる

『モシュリーマン……』。モシュって? 喪主ですよ! だからモシュリーマンと著者は言うのです。平凡なサラリーマンが、ある日突然、父の訃報に接して、葬儀の知識もないままに喪主となる戸惑いと緊張の記録です。旅行先で突然電話を受けて、四十九日を終えるまでの数々の出来事と対応を、リアルに描いています。
『小説道場』ほか中島梓の電子本、2500部到達!
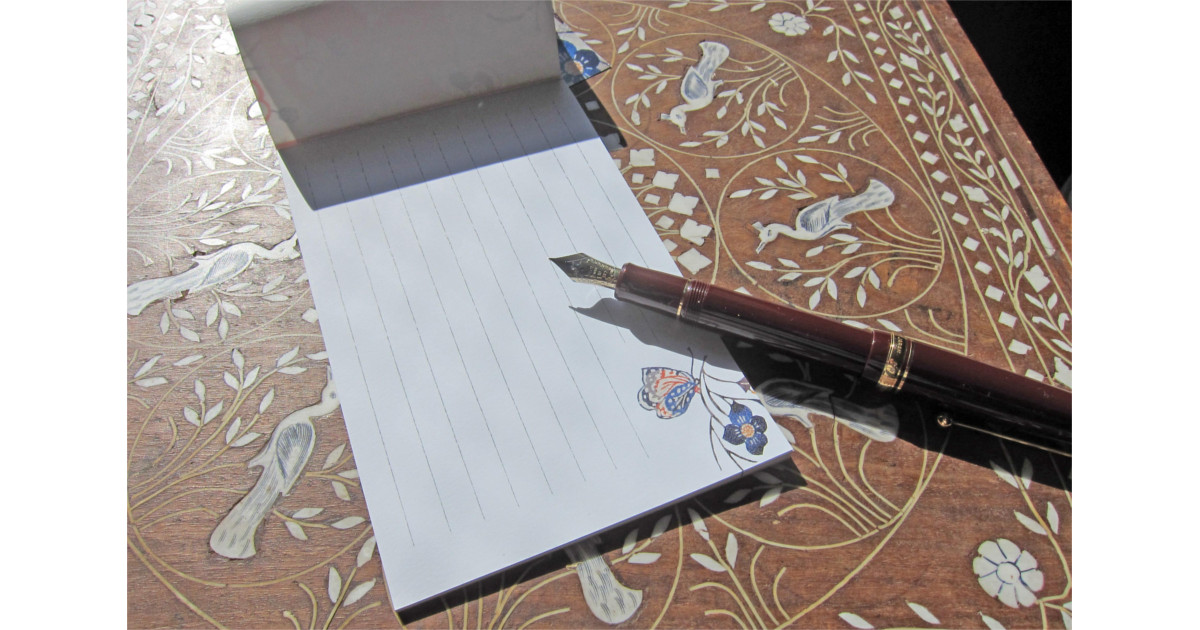
「ケータイ小説の女王」がセミナーにゲスト登壇(2018/6/9 渋谷)

西郷隆盛のホンモノの写真がある?!

マンガ家・羽賀翔一を読もう

それは化石の発掘のように…写真から迫る西郷隆盛 本当の”顔”

西郷隆盛といえば、坂本龍馬や伊藤博文などと並ぶ、明治維新の有名人。薩摩藩を動かし、薩長同盟や江戸無血開城に功績のあった、現代日本の基礎となった偉人の一人です。
その隆盛は、どんな顔をしていたのか? 教科書やネットには、いかにも薩摩隼人らしい、ガッシリとした屈強そうな肖像が載っています。日本の夜明けを切り開いた「西郷どん」にふさわしい容貌です。
ですが、それは、本当に西郷隆盛の顔なのでしょうか?
東電OL殺人事件が歌舞伎に!? 小田切しん平が魅せる戯曲の力
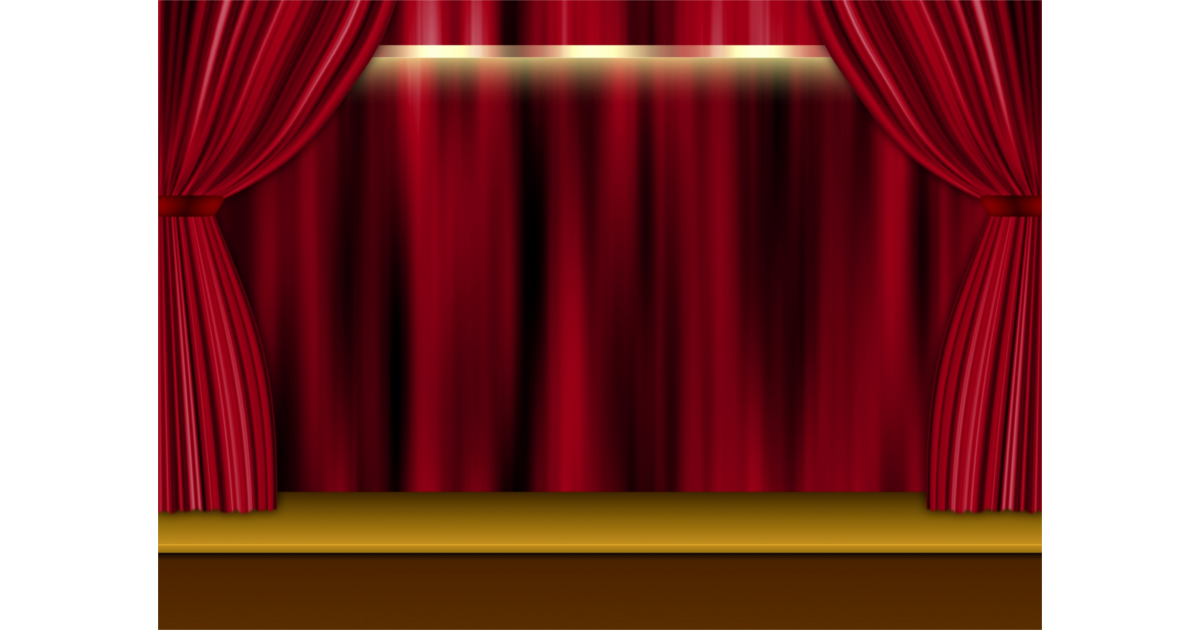
東日本大震災や東電女子社員殺人事件といった現代日本の重大事件を歌舞伎の題材とする。そんなことが可能なのか? 『小田切しん平 劇作集』では、それを実行しています。そして、その手法には前例があります。江戸時代元禄期に起きた赤穂事件を題材として、室町初期の物語として制作された『仮名手本忠臣蔵』です。直接、大名の醜聞を取り上げることを禁じられた時代で、文学の力によってマスメディアと社会批評の役割を果たした作品です。戯曲には、このような力があります。
小説、漫画、映画、アニメ……。「物語」を伝える媒体はさまざまです。その中で、「戯曲」という形式は、なじみのない人も多いかもしれません。有名な戯曲としては、やはりシェークスピアが挙げられるでしょう。ギリシア悲劇なども、よく知られています。そうした名作を読むと、台詞とト書きだけで構成された作品に、奥の深い物語の世界が広がっていることがわかります。戯曲もまた小説や映画に劣らない、人の心や時代を伝える表現の形式なのです。
想像つかないぞ! “8K”体験 NHK技研公開 5月24日から

教育はすぐに成果など現れない
学校の先生のことをみんなよくは言わない。最近はとくにどぎつい。私も当時はそんな一人でもあったかもしれない。申し訳ないとつくづく思う。というのも、今になってわかったことがあります。お話ししたい。
私は東京の品川区にある都立高校に通っていた。担任は土方俊彦という英語の先生でした。先生はよく教科書から離れて本を読めと薄い英語のテキストを紹介した。サイドストーリーだと。私が読んだのは『Shooting an Elephant』と表紙に書いてあった。G・オーウェルの『象を撃つ』という名作だ。当時は何もわからない少年にすぎない頃であったから、深く考えることもなく題名のわかりやすいものを手に取ったわけだ。不思議というかラッキーだったというべきか私は『象を撃つ』を英文で読んだのです。その上に簡単な感想まで言った。考えられない稀有なる出来事でした。先生は見たこともない笑顔で私を見た。そしてロクでもない戯言の私の感想を聞いて頷いてくれた。もう一冊薄っぺらい英語のテキストを先生は私に渡した。これを読めと。そこに“John Steinbeck”と書いてあったことははっきりと記憶にあります。でもなんという題名の本であったか思い出せない。たしか……『人々を率いる者』だったか『???の少年時代』だったか……アメリカの内陸地、遠くに高い連山。つづく山々を見て少年は育つ。あの山の向こうに何があるのかといつも思いながら少年は成長し、ついに山の向こうへと旅立っていく……という話だったと思うが確かではない。読みきっていなかったのかも。スタインベックの名前とも映画『怒りの葡萄』の原作者ぐらいの関わりしかその後もなかった。

私の高校、東京都立八潮高校。戦前は府立第八高等女学校、その時代からの校舎だった古風な雰囲気から、鈴木清順監督の映画『けんかえれじい』のロケに使われて、「岡山第二中学校」にされてしまっていた。