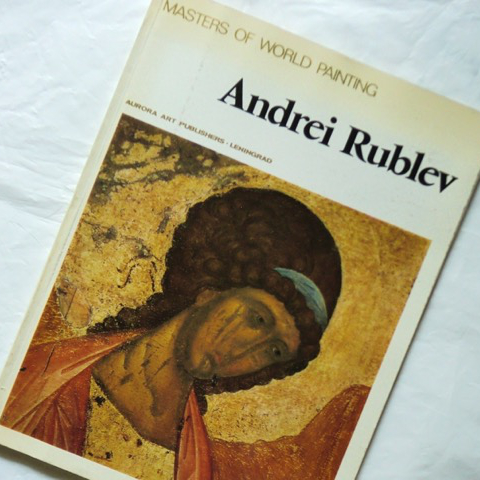
ピックアップ
2015年11月9日
何十年ぶりかでタルコフスキーの『アンドレイ・ルブリョフ』を見た。アンドレイ・ルブリョフは実在した15世紀ロシアのイコン画家であるが、動乱の時代を生き、創造の壁にぶつかりながら歴史的な絵画を描き残す。その放浪の過程で鐘造りの若者と出会う話が映画の最終章に出てくる。鐘造り親方であった父親を亡くし、残された若造とも言える息子がはじめて親父の跡を継ぐべく鐘造りに挑戦する。鐘は見事に完成し、鐘つき玉(舌)が揺れ動き、反動を大きくして、最後の最後に大きな音を発する。
 『アンドレイ・ルブリョフ』DVD
『アンドレイ・ルブリョフ』DVD
企画・制作・発売元:株式会社アイ・ヴィー・シーより
このシーンの中で息子は泥道の中に倒れこみオロオロと泣き崩れる。鐘造りの何一つも親父は息子に残さなかった。ものづくりの一切の不安と責任を背負って若者は挑み、やり遂げた。その輝かしき結果こそ、泥道の中に吐き捨てられるような自分の身体であったのだ。アンドレイ・ルブリョフは一切を目撃し、ボロ屑のように路傍に倒れた若者を抱きかかえる。立派にやり遂げたと。そしてお前を見て自分も再び絵筆を手にしようと。
ものをつくることの何と孤独で報われない姿かを思い知らされる。と同時に頼りないこの世界の中に、たった一人であったとしても全てを見とどける人の存在のあることを意識する。若者を確と抱きかかえる老いたるアンドレイ・ルブリョフの両手の愛おしさが、痛いように伝わって来る。